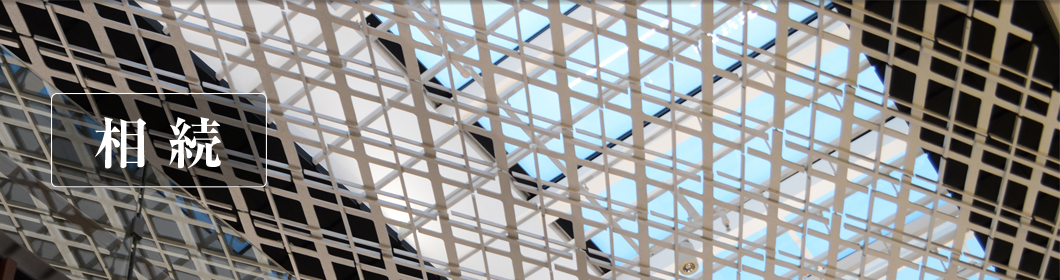
遺留分
遺留分とは
「遺留分」とは、一定の法定相続人に対して最低限度保障される被相続人が有していた相続財産に対する一定の割合のことをいいます。
具体的な遺留分の額は、父母、祖父母など直系尊属のみが相続人である場合については、相続財産の3分の1、配偶者、子などの場合には相続財産の2分の1が遺留分として確保されることになります。なお、兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。
遺留分侵害額請求権
相続をする場合、相続人が法定相続分に従って相続財産を承継するのが原則です。しかし、遺言の内容によっては、特定の相続人の遺留分を侵害することもあります。
そのような場合、遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対して、遺留分侵害額請求権を行使して、侵害された遺留分に相当する金額の支払いを請求することができます。
遺留分侵害額請求権を行使できる者は、前述のとおり遺留分が認められている配偶者、子など及び直系尊属です。
行使できる遺留分の範囲は、相続財産に2分の1を乗じた額に対して、自己の法定相続分をさらに乗じた額となります。直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産に3分の1を乗じた額に対して、自己の法定相続分をさらに乗じた額となり、配偶者、子などの場合には相続財産に2分の1を乗じた額に対して、自己の法定相続分をさらに乗じた額となります。
例えば、相続財産が2000万円、相続人が妻、長男、次男の3名で、長男に全ての相続財産を相続させる内容の遺言が存在するとします。
この事例で、長男に対して妻、次男が請求できる遺留分侵害額請求権の額は、妻が2000万円×2分の1×2分の1(法定相続分)で500万円、次男が2000万円×2分の1×4分の1(法定相続分)で250万円となります。
遺留分侵害額請求権を行使できる対象は、遺贈及び相続開始前の1年間になした贈与です。贈与を受けた者が相続人である場合には10年になります。
遺留分侵害額請求権の行使については、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間という短期消滅時効が定められています。
遺留分侵害額請求権の行使については、法令上特に定めがありませんので、訴訟を提起するほか、実務上、遺留分侵害額請求権を行使したことを明らかにする趣旨で、内容証明郵便が用いられます。
遺留分侵害額請求権は金銭を請求するものなので、急に多額の現金を用意することができず、支払いに窮する相続人が発生することを踏まえ、裁判所により、相当の期限を設けて支払いを猶予する制度が設けられています。
遺留分減殺請求権
平成30年相続法改正により、遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権に変更されました。施行日である令和元年6月30日以前に発生した相続については、遺留分侵害額請求権ではなく、遺留分減殺請求権が行使できました。
遺留分侵害額請求権との最大の相違は、遺留分減殺請求権を行使した場合、当該行使者は、侵害されている遺留分額に応じて、対象となる財産の持分を取得することとなる点です。遺留分減殺請求権を行使により、株式や事業用資産が共有状態となることが、事業承継の妨げになるとされていました。
経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例
概要
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)は、事業承継税制、事業承継時の金融支援措置、そして「遺留分に関する民法の特例」の3つ枠組みを柱とした事業承継円滑化に向けた総合的支援策の基礎となる法律です。
相続人の中から被相続人の後継者となる者を選択する場合、遺贈や死因贈与、あるいは生前贈与等を用いて、株式や事業用資産を承継させることが考えられるところ、これら株式や事業用資産は、評価額が高額になる例が多く、前記のとおり、相続人(但し、兄弟姉妹を除く。以下同じ。)には遺留分が認められていますので、仮に株式や事業用資産を一人の後継者に承継させた場合、相続人の遺留分を侵害することがあります。
また、前記のとおり、平成30年相続法改正前の相続について、遺留分減殺請求権を行使した場合、当該行使者は、侵害されている遺留分額に応じて、対象となる財産の持分を取得することになります。
そのため、被相続人の死後、遺留分減殺請求権を有する相続人から後継者に対して遺留分減殺請求が行使された場合、後継者に対してせっかく承継させた株式や事業用資産が相続人間で分散されることになります。
平成30年相続法改正により、遺留分減殺請求権は、遺留分侵害額請求権という金銭支払請求権に変更されたため、直ちに株式や事業用資産が相続人間で分散されることはなくなりました。もっとも、前記のとおり、株式や事業用資産の評価額が高額化する例が多いことから、多額の遺留分侵害額支払義務を負担することによって、場合によってはその支払いのために、株式や事業用資産を処分して金銭を捻出しなければならない場合も想定されます。
このように遺留分を巡って円滑な事業承継が阻害されることを防止するために定められたのが、上記「遺留分に関する民法の特例」(以下「民法特例」といいます。)です。
民法特例を活用した場合、被相続人の生前に後継者を含めた推定相続人全員の合意のうえで、被相続人となる者から後継者に対して贈与等が行われた株式や持分(以下「株式等」といいます。)について、①遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)、又は②遺留分算定基礎財産に参入する価格を合意時の時価に固定することができます(固定合意)。
また、③①又は②の合意をする際に、併せて、株式等以外の事業用資産についても、①と同様に遺留分算定基礎財産から除外する旨の合意をすることもできます。
①及び③により、他の相続人は、株式等及び株式等以外の事業用資産について、遺留分の主張ができなくなります。そのため、相続に伴って株式等及び株式等以外の事業用資産が相続人間で分散化されることが防止できます。また、相続法改正がなされた後では、遺留分侵害額請求権となったことから、持分が分散化されることはなくなりましたが、民法特例を利用することにより、後継者において予想外の多額の金銭債務を負担することを防止できます。
また、②により、株式等の価値が急激に変動した場合でも、予期しない多額の出費を負担することを防止できます。
例えば、現時点では1株5万円の株式があり、これが被相続人の死亡時点では15万円に値上がりする場合を想定すると、固定合意を利用しない場合、1株15万円として遺留分の算定を行う必要があるのに対し、固定合意を利用する場合、1株5万円として遺留分の算定を行うことで足りることになります。そのため、遺留分侵害額請求権を行使された場合に不測の債務を負担するリスクを防止することができます。
このように、民法特例を利用することで、遺留分侵害額請求のリスクを軽減し、事業承継を円滑に進めることが可能となりますので、事業承継を検討している事業者・経営者の方は、是非とも活用を検討するべき制度です。
もっとも、民法特例を利用するためには、以下の要件を充たしたうえで、推定相続人全員の合意と経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
- 中小企業者であり、かつ合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること
- 被相続人となる者が過去において会社の代表者であったか又は合意時点において会社の代表者であること
- 後継者が合意時点において会社の代表者であり、かつ現経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、会社の議決権の過半数を保有していること
実務上大きく問題となるのは、推定相続人全員の合意です。
そのため、民法特例の利用を検討する場合には、あらかじめ推定相続人間で不公平が生じないようなスキームを構築し、かつ納得の得られる十分な説明を行い、理解を得ることが重要となります。
なお、個人事業者の事業用資産の後継者への贈与についても民法特例を利用することできます。但し、先代経営者はその有する事業用資産の全部を贈与する必要があります。このようなスキーム構築や説明については、事業承継に精通した弁護士に相談することが必要不可欠です。


